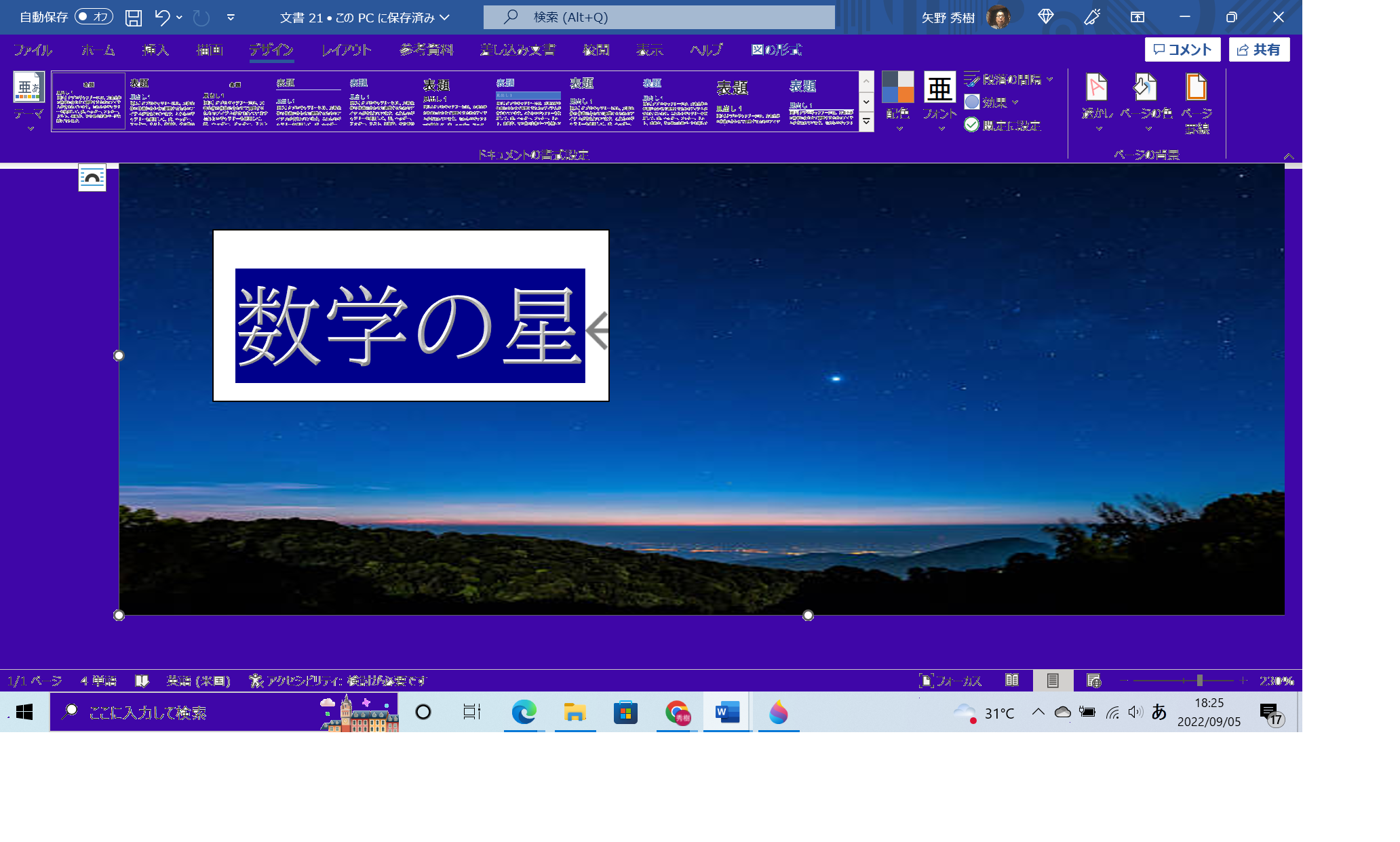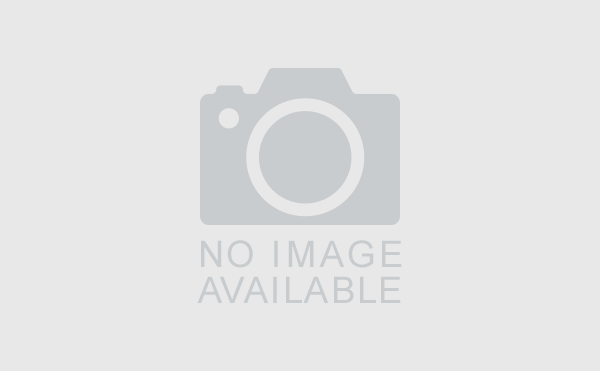これからの教師に必要な資質:教育改革の波に乗れるか?老教師のつぶやき
はじめに:センター試験廃止、その先にあるもの
皆さん、こんにちは。大学で教育学を教えている教授です。2020年から、あの馴染み深いセンター試験が姿を消し、新たな入試制度が始まるのです[1]。でも、これはほんの序章です。教育界全体が、大改革の渦中にあるのです。
第一章:知識の「習得」から「活用」へ
が、実は日本の教育には大きな課題があったのです。知識偏重で、その知識を実際に使う力が弱かった。つまり、「知っている」けど「できない」。これじゃあ、AIに仕事を奪われてしまいます。[2]。
そこで文科省が打ち出したのが、「知識の活用」を重視する新しい教育スタイル。暗記中心からの脱却を図り、思考力・判断力・表現力を育成することが求められています[3]。実際長年愛用してきた黒板がタブレットに代わりました。
第二章:日本の学校教育に欠けているもの
さて、ここで皆さんに問題です。もう一つの課題として日本の学校教育に欠けているものは何でしょうか?正解は...「多様性」です!
これまでの日本の教育は、「みんな一緒」「横並び」を重視してきました。でも、グローバル化が進む世界では、多様な価値観や能力を認め合い、それぞれの個性を伸ばす教育が必要なのです[4]。つまり、「一斉授業」から「個別で最適化された学び」への転換が求められているわけですね。
第三章:教師の精神性が変革の鍵
ここで、ちょっと厳しいことを言わせていただきます。実は、教育改革の最大の障壁は...教師自身の固定観念なのです。
答は一つである。一つだけの答えを要求する。それは授業内だけでなく生徒指導、生活指導全般にわたっていました。「こうあるべき」「これが正しい」という思い込みが、新しい教育スタイルへの適応を妨げています[5]。まるで、スマートフォンを手に入れたのに、電話とメールしか使わないお年寄りのようなものです(私のことではありませんよ!)。
第四章:教師の新たな役割
では、これからの教師に求められる役割とは何でしょうか?それは、「教える人」から「学びを支援する人」への転換です[6]。
生徒の好奇心を刺激し、自ら学ぶ力を引き出す。そして、生徒一人ひとりの個性に合わせた学習環境をデザインする。アクティブラーニングのように個別で得られた知識を統合して「実際に活用できる」形で。
おわりに:未来の教育を創る
さて、これから教員を目指す若い皆さん。大変な時代に教師になろうとしていますね。でも、それは同時に、教育の歴史に新たな1ページを刻む、とてもワクワクする時代でもあるのです。
AIやテクノロジーを味方につけ、生徒一人ひとりの可能性を最大限に引き出す。そんな未来の教育を、皆さんの手で創っていってください。私も、杖をつきながら応援しています!
参考文献: [1] 文部科学省. (2017). 「高大接続改革の実施方針等の策定について」 [2] 石川一郎. (2017). 『2020年からの教師問題』. ベスト新書 [3] 中央教育審議会. (2016). 「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について(答申)」 [4] OECD. (2018). The Future of Education and Skills: Education 2030 [5] 佐藤学. (2015). 『専門家として教師を育てる』. 岩波書店 [6] Hattie, J. (2012). Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact on Learning. Routledge