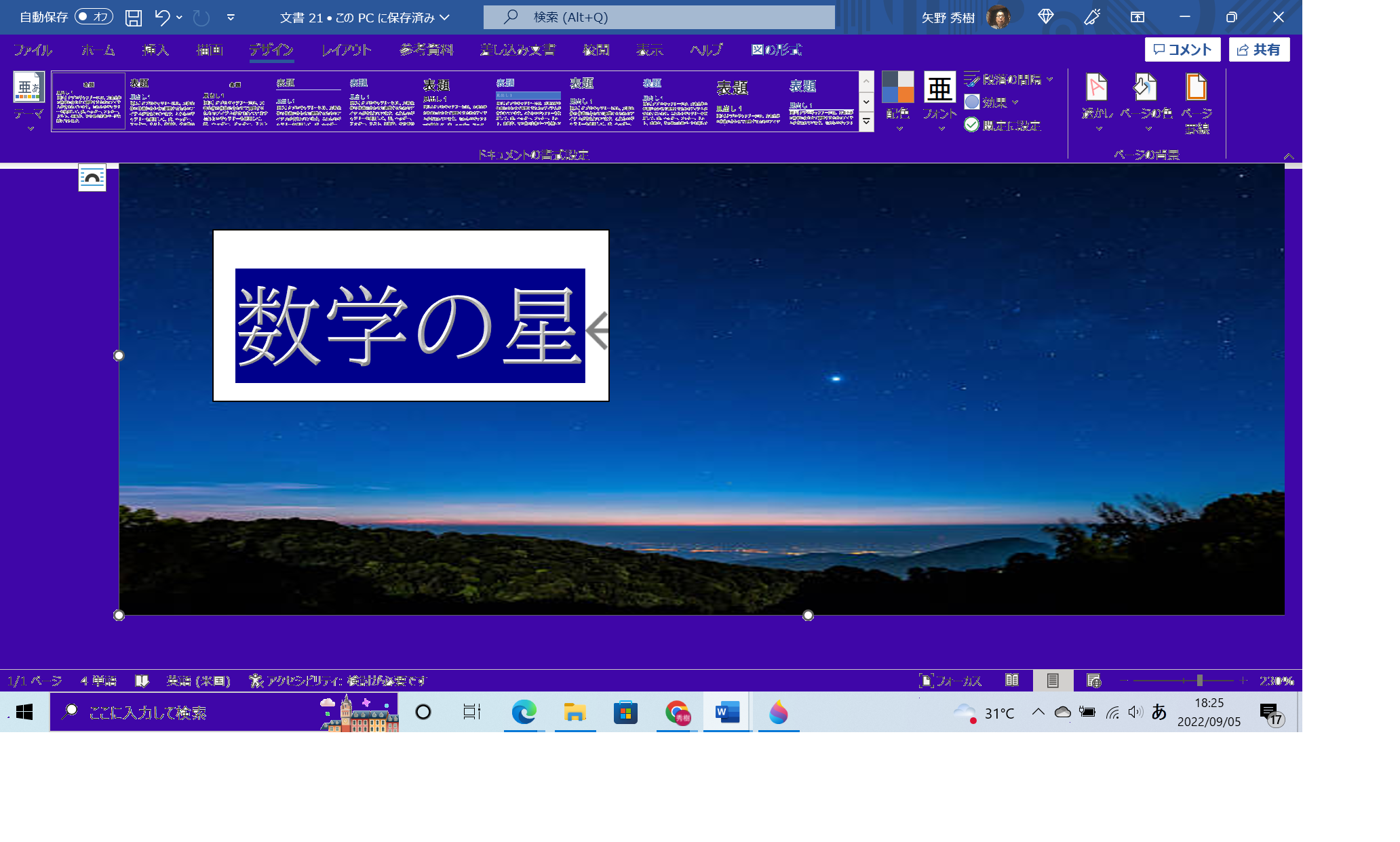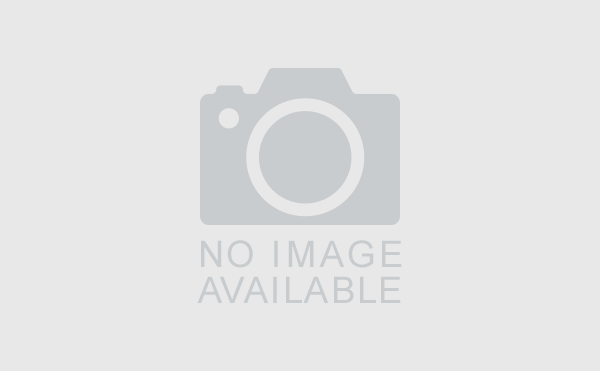不親切教師の勧め
若き教育者の皆さんへ
こんにちは、大学で教鞭を執る者です。 今日は、松尾英明先生の「不親切 教師のすすめ」という、一見すると挑発的なタイトルの本について、皆さんと一緒に考えてみたいと思います。
「不親切」の真意を探る
「不親切」という言葉を聞いて、少し驚かれた方もいるかもしれません。 しかし、ここでいう「不親切」とは、子どもたちの自立心や主体性を育むための、ある種の「愛のある距離感」を指しているのです。
アドラー心理学との関連性
本書はアドラー心理学の観点から書かれています。 アドラー心理学では、人間を社会的存在として捉え、自立と協調の重要性を説いています。 松尾先生の提案する「不親切」な教育法は、まさにこの考えに基づいているのです。
7つの提言を紐解く
1.「楽しい授業」をやめる: これは、学びの本質が「楽しさ」だけでなく、時には困難を乗り越える経験にもあることを示唆しています。 受け身ではなく主体的に学ぶ生徒の育成が必要であるという点。
2.習字の掲示をやめる:個々の作品を比較することで生まれる競争心や劣等感を避け、子どもたち一人ひとりの成長に焦点を当てる提案です。
3.「してあげる」をしない:本来子供がすべきことを教員が肩代わりしてしまうことをしない。 子どもの主体性向上をはかるために様々な場面で子供の失敗するチャンスを奪わないこと。 例えば「常にに屋外で遊ばせない」などのことをする。 子供は転ぶことなどから、危険回避能力や、危機管理能力を獲得していきます。 過度な手助けを控えることの大切さ。
4.「揃える」をやめる:個性を尊重し、画一的な指導を避けることの重要性を強調しています。
5.「きちんと座りましょう」のナンセンス:動き回る児童などの指導に際して「動くな」一方的な指導は逆効果になる場合が多いです。
「いつでもやっていい」というと、必要な時以外はあまりやらなくなる事例も多いようです。 本人の意思として身体を自由にすることでその児童そして教室全体が落ち着くこともあります。
6.かわいい子には:子供の危険対処能力を育成する。 危険要素を除外するのではなく。 むしろ「危険の中でこそなされる」べきことである。
7.子供の家庭を覗かない: 家庭でも不親切教育をすすめる
新しい教育観への招待
皆さんは子どもたちの未来のために日々奮闘されていることと思います。
時として私たち教師の「親切心」が、子どもたちの成長の妨げになっていないか、立ち止まって考えてみる必要があるのではないでしょうか。 この本は大きな刺激となります。